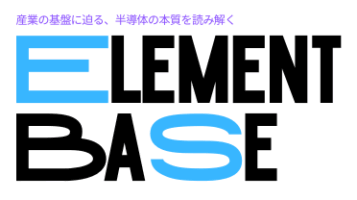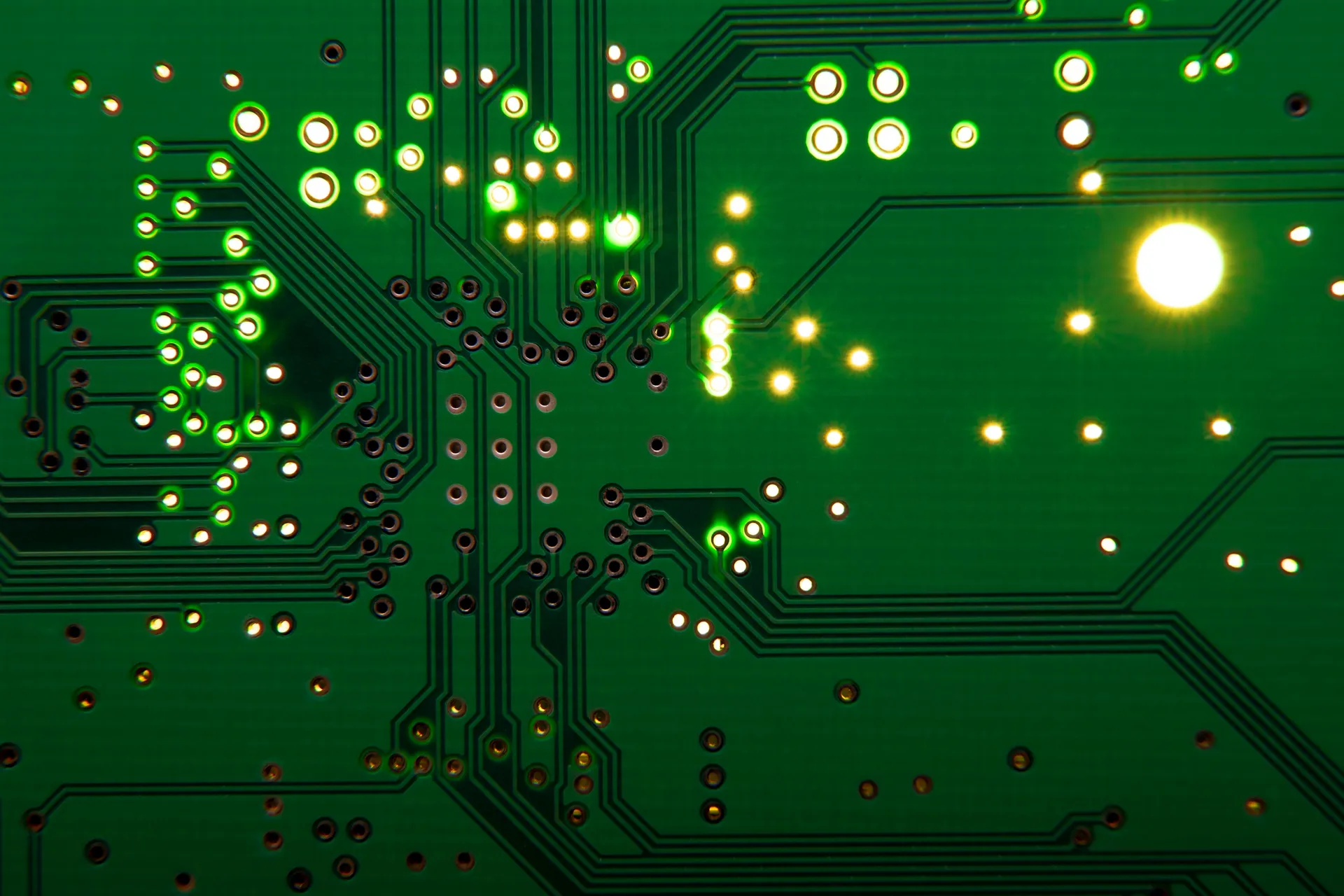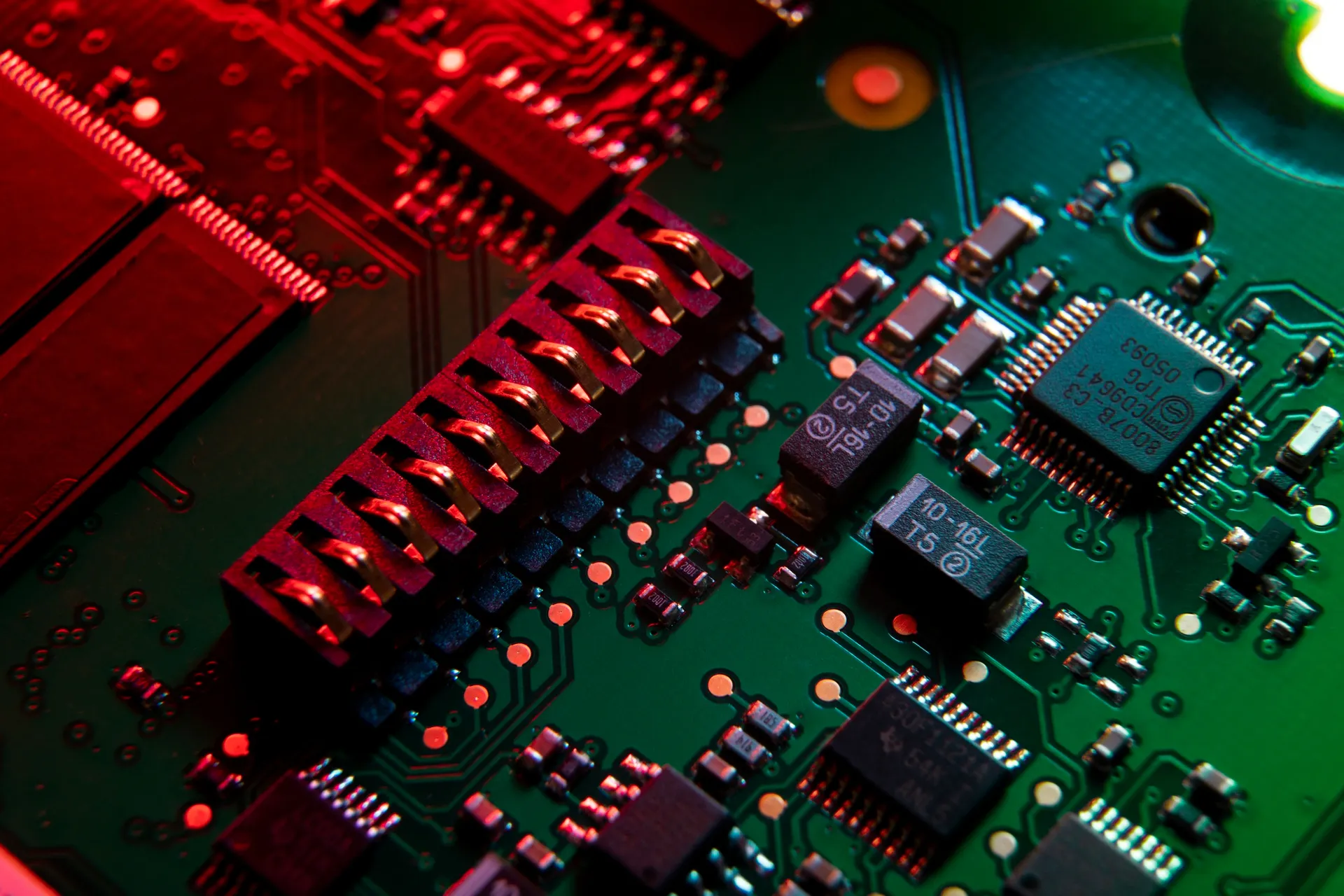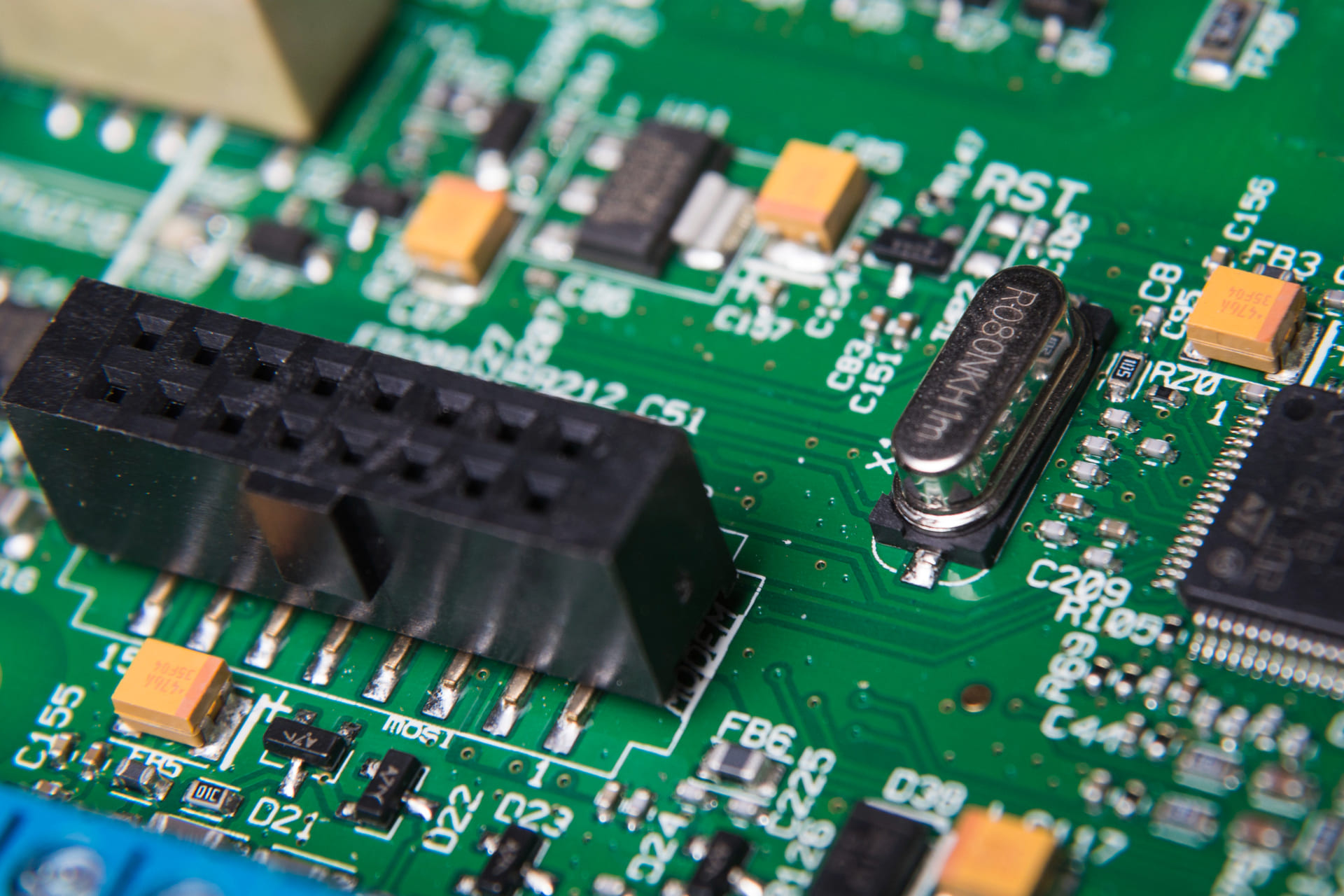「産業の米」とも称される半導体は、自動車や家電、スマートフォンから通信インフラ、医療機器に至るまで、私たちの暮らしを支えるあらゆる製品に組み込まれています。
しかし2020年以降、コロナ禍や国際的な物流停滞、地政学リスクの高まりといった複数の要因が重なり、世界的な半導体不足が発生しました。とりわけ自動車や家電などでは深刻な供給難が続き、社会や経済に広範な影響をもたらしました。
本記事では、なぜ半導体不足がここまで深刻化したのか、その影響がどのように波及し、今後どう回復へと向かっていくのかを多角的に整理し、私たちが直面する課題と備えについて考察します。
半導体不足が突きつけた社会への影響
近年、社会全体を揺るがす深刻な半導体不足が発生し、世界中で大きな波紋を広げました。かつては産業界の裏方として語られることの多かった半導体が、今や私たちの生活や経済、安全保障にまで影響を及ぼす「見えないインフラ」であることが、広く知られるようになったのです。
自動車の納車遅延、家電の品薄、医療機器や通信インフラの供給不安など、半導体不足はあらゆる分野に実際的な混乱をもたらしました。
本章では、こうした社会的影響を多角的にとらえ、なぜここまで深刻な事態となったのか、そして今後どのように備えるべきかを読み解いていきます。
産業を支える「見えないインフラ」の脆弱さ
半導体は、クルマやパソコンはもちろん、冷蔵庫や洗濯機に至るまで、あらゆる機器に搭載されています。多少なりとも知的な機能をもつ製品には、ほぼ例外なく半導体が組み込まれているのが現代です。そのため「半導体が使われていないものを探すほうが難しい」とまで言われるようになりました。
2020年以降の半導体不足は、私たちの生活や産業全体に深刻な影響をもたらしました。とくに自動車業界では、MCU(マイコン)の供給難により減産や操業停止が相次ぎ、新車の納期遅延や中古車価格の高騰を引き起こしました。家電分野では、冷蔵庫・洗濯機などの白物、テレビ・録画機器といった黒物家電の入手が困難となり、リードタイムの長期化も発生しています。
こうした製品群に使用される半導体は、最新技術ではなく、比較的古い「枯れた技術」によるものが中心でした。メーカー側にとっては、まさかこうした旧式の半導体が供給逼迫を起こすとは予想外だったといえます。
医療・通信・生活インフラにも影響
半導体不足の影響は、医療現場にも及びました。たとえば、内視鏡や心電計、パルスオキシメーターといった生命維持や診断に欠かせない医療機器の部品供給が滞り、製造や修理の遅延が発生。とくに小型で高性能なイメージセンサーやMCU(マイクロコントローラ)は需要が高く、代替のきかない重要部品であったため、現場では深刻な機器不足を招く事態となりました。
さらに、通信・金融・交通といった生活インフラにも影響が広がりました。ルーターや基地局の納期遅延により、インターネット通信の安定性が損なわれる場面があり、テレワークやオンライン授業にも支障をきたしました。ATMや券売機の部品供給が滞ったことで、一部の金融機関や交通機関では保守・更新作業が遅れ、利便性や安全性が損なわれた例も報告されています。
加えて、皮肉なことにこの半導体不足は、半導体製造装置そのものに使われる部材の不足も引き起こしました。露光装置、エッチング装置、搬送ロボットなどの製造装置に搭載されるセンサーや制御用ICが足りなくなり、新たな生産ラインの立ち上げが遅延。その結果、さらなる半導体不足を招くという「供給不足が供給不足を生む」悪循環が形成されたのです。
こうした連鎖的な影響は、企業活動だけでなく、私たちの暮らしの根幹にも静かに忍び寄りました。今や半導体は、目には見えなくとも生活を支える不可欠な社会インフラであることが、誰の目にも明らかになったといえるでしょう。
半導体の供給回復は「まだら模様」
2020年後半から始まった深刻な半導体不足は、2024年に入って一部の分野でようやく改善の兆しが見え始めました。しかしその回復状況は分野によって大きく異なり、「まだら模様」と表現されるのが実情です。
とくにAI・IoT・EV(電気自動車)・5Gといった先端分野では、依然として需要が供給を上回る状況が続いています。これらの分野は技術革新のスピードが速く、半導体に対する品質や処理能力、低消費電力性能などの要求も高いため、製造体制の整備が追いつかない状況です。また、こうした用途向けの最先端プロセスノードに対応できる製造装置や素材も限られており、設備投資には巨額の資本と時間が必要となります。そのため、供給体制の本格的な整備と安定化は2025年以降にずれ込むと見られています。
一方で、家電製品や既存型のスマートフォン、PCなどに使用される従来型のロジックICやアナログICについては、供給が徐々に安定しつつあります。これらは比較的成熟したプロセスノードで生産されるため、既存設備の活用が効きやすく、回復が早く進んでいるといえます。
ただし問題は、こうした製品群の半導体は利益率が低く、ファウンドリ各社にとっては積極的な投資対象になりにくい点です。結果として、需要と供給が均衡しやすい反面、生産調整や設備停止が起こりやすく、突発的な需給ひっ迫の再発リスクも抱えています。
つまり、半導体供給の回復は単なる数量の増減では語れず、用途別・製品別に見た中長期的な需給戦略と産業構造の再構築が問われている段階にあるのです。
世界情勢が与える影響と今後の備え
半導体は、もはや単なる電子部品ではなく、経済安全保障や国家戦略にも直結する「戦略物資」として世界各国が注目する存在です。近年、米中の覇権争いやウクライナ侵攻、中東情勢の不安定化など、地政学的リスクが頻発しており、これらが半導体サプライチェーンの安定性に深刻な影響を与えています。
特に、最先端プロセスを担う台湾・韓国に生産が集中している現状は、サプライチェーンの「一点集中リスク」として各国の政策に影響を与えています。アメリカではCHIPS法に基づく国内回帰の推進、日本でも経産省主導でのラピダスや熊本のTSMC誘致など、国家レベルでの生産基盤の再構築が加速しています。欧州連合(EU)も自給率向上を掲げ、各国で技術主権の確保に向けた動きが活発化しています。
また、過去を振り返っても半導体産業は幾度となく“シリコンサイクル”と呼ばれる需給の波を経験してきました。短期的なブームと急落を繰り返すなかで、過剰投資や供給過多、突然の設備縮小といった事例も後を絶ちません。
今後も、新たなパンデミックや自然災害、あるいは外交摩擦などにより、同様の供給混乱が再発する可能性は十分に考えられます。企業にとっては、複数の調達先を持つことや在庫戦略の見直し、代替品の確保などが重要なリスクマネジメントとなります。個人レベルでも、情報機器の調達時期やスペック選定において、「供給リスク」や「更新タイミング」の視点を持つことが求められる時代となりました。
世界情勢の変化が直結する今、半導体に関する知識と備えは、ビジネスだけでなく私たちの生活全体の安定に関わる重要なリテラシーといえるでしょう。
まとめ
世界的な半導体不足は、ただの供給問題にとどまらず、社会基盤そのものを揺るがす大きな教訓となりました。自動車や家電の減産、医療・通信インフラの不安定化、さらには半導体製造装置の供給難による悪循環まで、影響は広範囲かつ深刻でした。
2024年初頭には一部で改善の兆しが見られるものの、AIやEVなど先端分野では依然として需給がひっ迫しており、本格的な回復は2025年以降と見られています。今後は、各国の供給網再構築や備蓄戦略とともに、企業や個人が柔軟に対応するための備えがより一層求められる時代に入っていると言えるでしょう。半導体が社会の根幹をなす存在であることを、私たちは改めて実感させられています。